議事録
ゲストの川添良幸さんによる講演要旨
「心豊かな社会をつくるための思考法」

東北大学に入学してから来年で還暦を迎えます。それ以外の世界を知らない私が分かる範囲で、「科学と社会」意見交換・交流会における、これまでの講師の先生方の御講演や残された議論記録を読ませていただきながら私なりに考えた、心豊かな社会をつくるための思考法をお話しさせていただきます。
現在の日本の大学では「評価」が重視され、好き勝手な研究をやっている奇人・変人は居場所がなくなり、人の目を気にする風潮が強まっています。マスコミの取材でも、「自分の興味のあることをやっていたら、こんな面白い結果になった」と言うと、「何の役に立つのか?」と聞かれます。研究成果は引用回数やh-index等の「客観的」数値で表され、「心」の入り込む余地がなくなりました。これは社会一般でも同様と思われます。私の現在の研究内容は「計算機シミュレーションによる新有用材料設計」ですが、実は「計算機による仏教文献の研究」の方でより知られている世界もあります。本業の方は、35年ほど前にまるで素人の私を教授として呼んでくれた東北大学金属材料研究所の懐の深さに感謝しています。当時、誰も計算機シミュレーションで新材料設計開発など出来るとは思っていなかったのですが、実験研究だけでは行き詰まり、専門外の私に将来的可能性を見出してくれました。計算材料学という用語は私の造語です。大学院で勉強した理論ファーストの原子核理論を実験主体だった材料設計に適用するという方策です。
25年前に私が仙台で創立したACCMS(Asian Consortium on Computational Materials Science)はその後、大きな発展を見せてくれました。大きな学会等から賞をもらって喜ぶより、自分のやりたいことをテーマとする学会を作る方がよっぽど楽しいのです。これまでにアジア各地で30回以上の集会を開き、全てで創設者として歓迎されました。これ以上の楽しみはありません。ナノ学会も同様に私が名称を決めました。学会名は短いほど広い範囲を網羅できると思ったのですが、設立当初は「何の学会」と言われました。他の学会は対象物ごとの集まりだったからです。サイズがナノなら何でも良いという私の定義は功を奏して、現在は日本のナノバイオロジーの中心となってくれました。会員数は300名程のままですが、基本1セッションで全部の講演を聴くという形式を継続しています。大きな学会よりも心がこもったことが出来ますし、異分野融合も可能です。研究者は好きなことを好きにやりたいので、管理されるのは嫌いです。時間管理まで厳しくやられるとストレスが溜まり、ハラスメントも発生します。奇人・変人が時間を気にせずに集中して研究し、たまに大きな成果を挙げる、というのが大きな学問の府である大学のあるべき姿だと思います。心豊かになるための思考法は研究者よりも管理職が持つべきです。3年や5年で挙げられる成果などは限られたものです。若い研究者は長い目で育成しなければなりません。
古希を超えてから作った東北大学発ベンチャー「名誉教授ドットコム株式会社」は、地元貢献を謳い文句のひとつとしています。しかし、今のところ、首都圏や海外企業が主なお客さんになっています。何をやるかより誰とやるかの方が重要だという私の独自コンセプトでスタートしたのですが、地元企業はその日暮らしで忙しく、心豊かにとか言ってもなかなか大変そうです。「科学・技術の地産地消」を実現するために何某かの寄与をしたいと設立5年目にして地元重視の観点で再検討を行っています。
私の不思議な座右の銘は「トモダチ」です。これは園山俊二さんの「はじめ人間ギャートルズ」で、ゴリラのドテチンが人間とはじめて交わした言葉です。動物どころか神様まで皆トモダチにして、心豊かで争いのない社会を実現したいものです。

川添さんは講演で、たこ焼き器や月など、様々な身近な事例をあげ、参加者が体験できる実習も交えながら、「我々の脳は簡単に騙される。しかし、本質的に間違っていても生活には困らないため、実はとんでもない誤解をしていることもある。教科書問題は歴史だけではなく、数学や理科その他、何にでも沢山ある。間違っているからこそ、教科書を変える仕事=研究ができる」と、常識を問い直す必要性を説きました。
そして自国の歴史の捉え方についてもSDGsを例にあげ、「欧米では自然を征服して破壊してきた。それが限界に来ただけ。それを日本人が真似することはない。日本は『勿体ない』と、自然と融合して暮らしてきた。日本に誇りを持ってください。では、なぜ日本人は誇りを持てなくなったか。『WGIP(War Guilt Information Program)』を知っているか?GHQが日本人に誇りを持たないようにした。しかし日本には、1万年も続いた持続可能社会の見本のような縄文時代があり、文明的な社会だった」と自国に自信を持つ重要性を語りました。
その上で、日本の研究や教育の問題の本質を「すでにあるものを何とか改良しようという発想ではなく、新しいことをつくることをやらないと駄目だ」と指摘。「基礎研究は『役に立たない』と言われるが、奇人・変人は変革に役立つ」と、製造装置内に蓄積するインジウム(レアメタルの一種)を再利用する自らが実施した基礎研究がインジウムの価格高騰を抑制した事例等をあげ、「日本の将来のためには、単なる改良型の教育・研究ではいけない」と強く訴えました。

議論の様子(一部抜粋)
Q これまでの研究で一番面白かったことは?
A 本質的に「物性理論、例えばハバード模型が正しくない」と言えるようになったことが嬉しい。最初の頃は仕方がないが、ずっと間違い続けているのは駄目。「確実にこうだ」といくつか正しくないことを見つけられたのは、人生としては嬉しかった。
Q 最近は「AI」と言うだけで皆が信頼する、まるで宗教のようになっている。
A まるで水戸黄門のように盲目的。熱中症でアラートが出るセンサーを行政に売った時、我々が負けて、某業者が競争で勝った要因は、ある条件でアラートを出すレベルの大したことがない処理を「AI」と謳ったから。それに本当のプログラム教育が行われていない。学校でのプログラミング教育も、情報セキュリテイだの単に覚えるだけ。大学でも基本的な計算資源はすべてPythonなど、基本のルーチンは我々の世代が書いたものを使うだけになっている。顔認証だのを人工知能だと言っているのは、上書きプログラムでFortranのプログラムを呼んでいるだけなのに、皆、立派なことを言う。例えば、空港で顔認証が導入されるようになったが、どんな基準で機械が認証するようになったかをご存知だろうか?人間の審査員が間違う確率よりも、機械が間違わない確率の方がよくなったから。今までも間違っていたらしいが、機械の方が間違わなくなった。何でも100%はない。なんとなく皆、パーフェクトなものを期待するが、そんなことは不可能。現実問題として理想状態はできない。ある範囲の中で仕事をするしかない。
Q AIの進展に対して否定的な立場か?
A 悪いとは言っていない。そこそこ浸透していてよいと思う。問題は2つある。1点目は、AIでクリエイティブなことをやるには、他人のデータをもっと盗まなければいけなくなる。今のレベルのAIなら、クリエイティブなものは出てこない。2点目は自国が将来強くなるにはどうすればいいか、今とは異なるフェーズで戦略的に考えなければいけない。日本以外の国はそう捉えているのに、日本では今あるものを教え込み、勉強も「強いて勉めて」やらせて、使いやすい人間をつくるのが見え見えである。すると奇人・変人が住みにくい日本になる。大人しく洗脳された人たちの集まりでは、いつになっても、GDPの順位だって下落していく。自国の歴史をよくわかって暮らすようにしないと、勝ち目がない。現状のようなやり方では皆、疲れ果てて、働けども思ったより生産性が上がらない。真似事をしなくても、よい仕事はできるはずだ。日本の国が、心豊かな社会をつくるには、自分たちの文化に自信を持ち、自分の頭で考え、「志」を持つことが必要である。戦後、GHQによって日本がなくされてしまった「志」を取り戻す教育が必要だ。
宮城の日本酒
ざっくばらんな意見交換を促進することを目的として、季節の限定酒をご用意しました。なお、以下は用意した日本酒の銘柄、造り、使用米、精米歩合、製造年度を示しています。
1.黄金澤 大吟醸 山田錦40% 4BY
美里町の蔵 過去に歴代初16年連億金賞受賞の大吟醸
今年からは純米大吟醸の造りになり 最後の一本
2.乾坤一 大吟醸 山田錦40% 5BY
村田町の蔵 全国新酒鑑評会金賞 東北清酒鑑評会優等賞
3.日輪田 生モト純米大吟醸 雄 町40% 5BY
栗原市の蔵 萩の鶴 萩野酒造の 生モト造り別ブランド
昨年は正解の酒コンテストIWC最高トロフィー受賞
4. 鳳 陽 純米大吟醸 蔵の華40% 5BY
富谷市の 宮城県最古の蔵 IWC金賞受賞酒
5.日高見 純米大吟醸 助六 山田錦45% 5BY
石巻市 特約店販売酒 幕の内で気軽に楽しめる純米大吟醸
6.萩の鶴 中取り純米吟醸原酒 無加圧直汲み 美山錦48% 5BY
栗原市の蔵 精米48%の美山錦で造るスペックは純米大吟醸並みの純米吟醸
しぼる過程の真ん中部分 中取りを詰めました 無加圧直汲みはこの時期の限定品
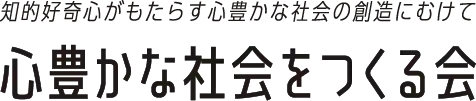


 [略歴] (かわぞえ・よしゆき)1947年宮城県仙台市生まれ。1966年3月東北学院中高等学校卒。1970年3月東北大学理学部物理第二学科卒業、1975年3月東北大学大学院理学研究科博士課程原子核理学専攻修了、理学博士。1975年4月東北大学教養部助手、1981年11月同情報処理教育センター助教授、1989年度から3年間、文部省視学委員、1990年5月東北大学金属材料研究所教授、同計算材料学センター長としてスーパーコンピューターの導入から運用に当たる。2005年4月東北大学情報シナジーセンター長(現サイバーサイエンスセンター)、この間、東北大学情報シナジー機構副機構長及び教員としては当時初めての事務職員兼務として同本部事務機構情報部長を併任。2012年3月定年退職。現在、東北大学名誉教授として同大未来科学技術共同研究センター内で研究を継続中。2020年4月、名誉教授の知恵と経験、ネットワークを生かしたコンサルタント会社「名誉教授ドットコム株式会社」を設立し、企業や行政等に助言等を行っている。上記現職の他、日本半導体デバイス産業協会理事、NPO法人日本語教育e-learningセンター副理事長などを歴任。東方学術賞(Eastern Prize)、科学技術情報センター学術賞、The Ken Francis Award、日本金属学会学術功労賞、IBM Shared University Research Award、ACCMS賞等を受賞。
[略歴] (かわぞえ・よしゆき)1947年宮城県仙台市生まれ。1966年3月東北学院中高等学校卒。1970年3月東北大学理学部物理第二学科卒業、1975年3月東北大学大学院理学研究科博士課程原子核理学専攻修了、理学博士。1975年4月東北大学教養部助手、1981年11月同情報処理教育センター助教授、1989年度から3年間、文部省視学委員、1990年5月東北大学金属材料研究所教授、同計算材料学センター長としてスーパーコンピューターの導入から運用に当たる。2005年4月東北大学情報シナジーセンター長(現サイバーサイエンスセンター)、この間、東北大学情報シナジー機構副機構長及び教員としては当時初めての事務職員兼務として同本部事務機構情報部長を併任。2012年3月定年退職。現在、東北大学名誉教授として同大未来科学技術共同研究センター内で研究を継続中。2020年4月、名誉教授の知恵と経験、ネットワークを生かしたコンサルタント会社「名誉教授ドットコム株式会社」を設立し、企業や行政等に助言等を行っている。上記現職の他、日本半導体デバイス産業協会理事、NPO法人日本語教育e-learningセンター副理事長などを歴任。東方学術賞(Eastern Prize)、科学技術情報センター学術賞、The Ken Francis Award、日本金属学会学術功労賞、IBM Shared University Research Award、ACCMS賞等を受賞。
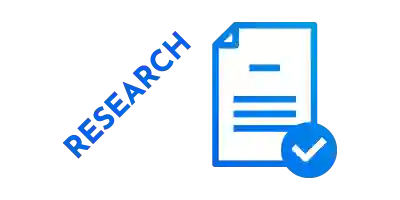
イベント実施報告一覧に戻る