議事録(概要)
ゲストの江刺正喜さんによる講演要旨
「オタクあがりのモノづくり人生」
江刺 正喜 ((株)メムス・コア、東北大学)
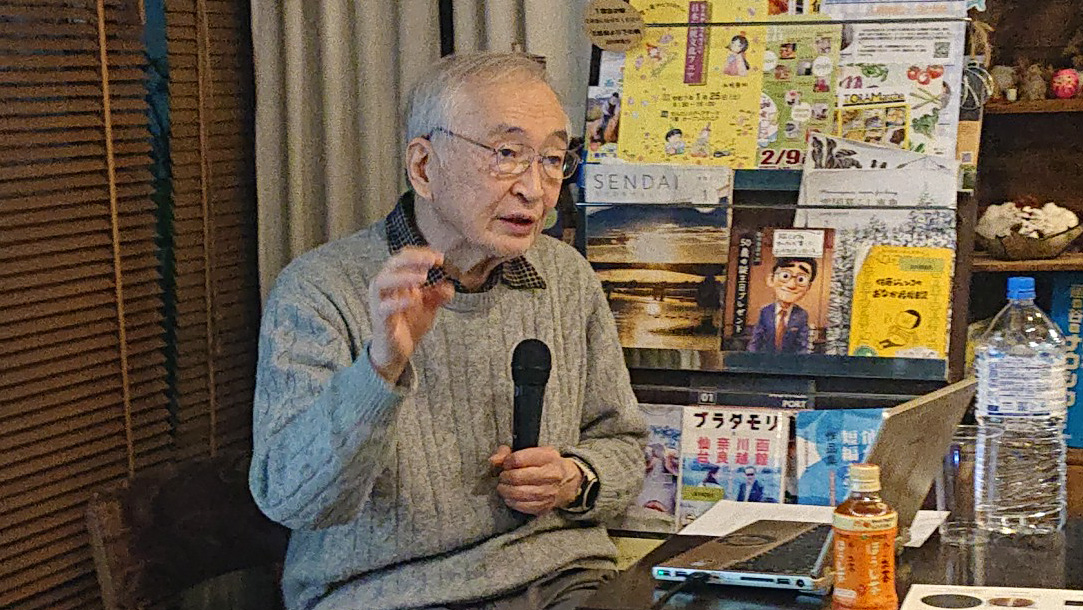
1.はじめに:MEMSとは
半導体微細加工をベースに多様な知識でセンサなどを作るMEMS (Micro Electro Mechanical Systems) と呼ばれる技術に、学生時代から半世紀ほど関わってきた。半導体の世界で、微細化・高集積化の「More Moore」に対し、MEMSは多様化の「More than Moore」と呼ばれる流れで、システムの入出力部などで鍵を握る高付加価値の部品を供給する技術。MEMS技術の応用は、自動車関連技術の発展に代表されるように、1980年代から排ガス規制をクリアするためにエンジン部分に圧力センサが用いられ、90年代からエアバックが搭載されるようになると加速度センサが用いられ、2000年代からは安全装置にジャイロセンサが用いられてスピンしなくなったように、車の高度化に対応している。自動運転の先駆け技術である距離画像センサ(LiDAR)は、地下鉄の飛び込み防止用ホームドアにも実装されている。鉄道の乗り心地を改善するための列車動揺測定装置は、GPSの電波を受けられない原子力潜水艦のナビゲーション用に開発された静電浮上ジャイロセンサの技術を応用したもの。加速度センサやジャイロセンサは、スマートフォンやゲームなどのユーザーインターフェースへと展開されるようになり、生活に身近な技術となっている。
高密度集積回路(LSI)などと異なり、MEMSは多品種・少量であることが多いが、開発がボトルネックになる。その場合の開発には一連の半導体微細加工の他にもいろいろな設備が必要で、また広い分野の知識にアクセスできる必要がある。このため自由度が高い一連の設備を共用しながら、使い方や関連知識を伝えて利用してもらう「試作コインランドリ」が、仙台市青葉台にある東北大学の西澤潤一記念研究センターにあり、戸津健太郎教授がセンター長として運営している。2010年に設置され、それ以来400程の機関 (334社) が人を派遣して利用し、独立採算に近い形で運用されている。利用者からの要望を行政に伝え、2013年から製品製作もできるようになっている。またサンプルなどを見られる5部屋の展示室や、知識提供に役立つようにExcelのキーワード検索で探せる1,000冊の文献ファイルなどがある。このような仕組みに至った経緯をお伝えすることで、役に立つ仕組みづくりにつながるような話をさせて頂きたい。
2.学生時代:装置自作
子どもの頃から工作が好きで、高等学校で物理部に入った時に先輩がやっている真空管の実験などを見て電子回路に興味を持った。その後、科学雑誌などを見ながら真空管やトランジスタでオシロスコープなども作った。東北大学で電子工学科に入ってから、この回路オタクが役にたち、そのまま定年後までモノづくりを楽しむ人生を過ごしてきた。
東北大学には“ミスター半導体”と呼ばれ、半導体を初期から研究し産業支援をされていた西澤潤一先生がおられた。西澤研の回路製作を手伝った関係で、西澤先生から大事にされた。西澤研にいた博士課程の学生のCV (静電容量-電圧) 測定器を作ったのがきっかけで、西澤研で実験させてもらい、その設備を参考にして20 mm角のSiウェハを処理する半導体製造設備を自作した。この設備はその後も使われている(写真1)。

【写真1】自作設備による試作実験室
私が大学院に入った1971年に、インテルより絶縁ゲートFET (Field Effect Transistor)を用いた最初のマイクロプロセッサ4004が発表された。この年に私の指導教官であった松尾正之先生がスタンフォード大学に留学され、私は最新の情報に接することができた。先輩の田頭功氏は生体用電極などのセンサ、また山本光章氏は心電図の自動解読などの新しい分野を開拓してくれた。
私は大学院で、絶縁ゲートFETのゲート絶縁膜を電解液に露出させて液中のイオン濃度を測定するISFET (Ion Sensitive Field Effect Transistor、技術遺産「第10回でんきの礎」として2017年3月に顕彰)を開発し、MEMS技術で幅0.5mmのプローブに加工してカテーテル先端に装着した。日立製作所で製作されたMOSトランジスタを用いて、その一部の50マイクロメートルほどのゲート部分だけを残してワックスで絶縁し、電解液に触れるようにして液の電位やイオン濃度を測るわけだが、当時は、爪楊枝を使ってトランジスタにワックスを塗っていたため、器用だと皆に褒められ、「ゴールド・フィンガー」と呼ばれた。しかしゴールド・フィンガーでは製品にならないので、センサ部分をプローブの形状にして、カテーテルなどの先に取り付けられるようにし、1983年に株式会社クラレより商品化された(1980年に薬事法で認可)。その後、日本光電工業株式会社に移管され、逆流性食道炎の診断などに多く用いられた。
西澤研の真似をして装置を自作した学生時代。博士課程で書いた論文は一つだけで、装置製作ばかりやっていたが、その後、この自作の装置が大変に役立った。自由度の高い一連の装置ができたため、会社の人が来て開発するようになった。今の学生は論文数が要求されてプレッシャーが強いが、当時は自由度が高かったのでよかった。
3.助手時代:設備共用
学生時代は一人でやっていたが、助手になってから学生と一緒にカテーテル用圧力センサなどを開発した。この頃、隣の研究室の新妻弘明助手と一緒に設備を共用する「マイクロ加工室」を整備した。ものづくりには設備が必要で共用が不可欠のため、教授会で認めていただき一講座分のスペースを使わせていただいた。
4.助教授時代:集積回路の製作
1981年、助教授になった時に計算機関係の伊藤貴康先生の研究室に移って集積回路(IC)を作ることになった。自作設備と、修理した中古のイオン注入装置でウェハ工程を行った。設計環境が無かったが、当時大学間にあった電話回線を使った計算機ネットワークを用い、京都大学で開発された論理シミュレータを使わせて頂いた。ICレイアウト用のグラフィックエディタはFortranで自作したが、これはプログラミングを覚える良い機会になった。製作したICを試験するICテスタもDEC社のミニコンに外付けの回路として自作したが、これもディジタル回路を勉強するのに役立った。当時はプリントアウトしたパターンを自作のカメラで縮小してフォトマスクを作り、チャネル長10 μmのCMOSICなどを製作した。研究室の学生には、4年生で前期にシミュレーションなどで設計して、後期にICの製作工程を経験してもらった。「半導体集積回路設計の基礎」(培風館、1986)という本を出版した。開発したMEMSとICを一体化した「集積化容量型圧力センサ」は、エアコンのフィルタの目詰まり検知などに20年以上使われた。また他の研究室のICも作った。
5.教授時代:オープン化と産学連携
1990年、機械系に移って教授になった。この時代になると企業では1MDRAMのようにチップ上にトランジスタが100万個も載っていたが、研究室では千個しか作れず、集積度が劣るためIC製作をあきらめた。
一方で、自作の装置は自由度が高く全工程を経験できるため、会社が喜んで利用してくれ、多くの企業が技術者を派遣してMEMSの開発を行った。約130社から利用され、各社から平均2年ほど、受託研究員が派遣された。そのうちの1990年から2004年まで人が来ていた会社を表に示す(表1)。自動車会社および自動車関連会社にマークしてあるが、競合する会社も一緒に発表し合うオープンな形で行った。企業からの人たちがモチベーションを持って仕事をするのは学生に良い刺激となった。

【表1】会社から派遣された受託研究員 (1990年-2004年)
当時は、日本の経済成長が低迷し、国もなんとかベンチャービジネスを支援しようと、ベンチャービジネスラボラトリ(現在のマイクロ・ナノセンター)という施設を作ってくれて、私が代表をさせて頂いた。大きな資金が使えたので、共同利用にして如何によい使い方ができるかを工夫した。講習を受けろとか面倒なことは言わずに、最も使う人が使い方を教えて自由度高く使えるようにした。
日本経済新聞社が行った産学連携特別調査(2003年12月12日付日経産業新聞)によると、我々の研究室は会社に最も頼りにされる研究室ということになっている。特許については、来た会社からお金を出してもらい、製品化するなら会社にあげるが、しないなら戻してもらい別の会社に使ってもらうようにした。実際に、ダイアフラム真空計の特許が競争相手の会社で製品化されたり、フォードで使われなかった技術が豊田中央研究所で製品化されたりした。大学は税金で運営しているので、他の会社を邪魔するような特許の使い方ならお断り。このような産学連携のやり方を「検証 東北大学江刺研究室 最強の秘密」彩流社(2009)(江刺正喜、本間孝治、出川通)に纏めた。
大学が独法化された時(2004年)、特許の扱いが問題になった。国の方針が「大学へのお金を減らすから、大学は自分で儲けろ」となったので、東北大学では会社でやったものを本学の単独出願にすると決めた。それに私は反対し、そのことが日経1面に掲載された。「大学さえよければよいというのでは、駄目だ」とボイコットしたら、大学が制度を変えてくれた。受託研究費として1社から300万円ずつ払ってもらうことで、毎年4,000万円程が集まり、国から資金を貰わずに運営できた。
「研究評価のパラメータは、研究成果 / 研究費用」(InterLab, 1996/6)と主張して、費用をかけずに役立つ成果をあげることを目指していた。2005年頃に、経済産業省の研究開発課から、産総研と共同で行うように頼まれた。縦割りの弊害の多い我が国にとって、これは良いことだと考えた。このため方針を変えて国の資金を使わせてもらうことにし、2009年度から 2013年度まで最先端研究開発支援プログラム(FIRST)「マイクロシステム融合研究開発」を行うことにした。
高密度集積回路(LSI)を受託生産するファウンダリにウェハ製作を頼むと、1回2,000万円かかる。そのため、この国の予算を使って、株式会社リコーやトヨタ自動車株式会社などと、LSIをファウンダリでウェハ上に乗り合いで製作してもらった。1990年にICの自作を断念していたのをこのような形で復活させ、複雑なLSI機能を持つ集積化MEMSを開発することにした。これには安全なロボットのため体表に触覚センサを分布させ、パケット通信でリアルタイムに接触を検知する触覚センサネットワーク(トヨタ自動車株式会社他と共同)、災害時に使えるワイヤレス通信機能(国立情報通信機構他と共同)、またLSIの試作や少量生産のためのマスクレス電子ビーム露光装置(株式会社クレステック他と共同)などがある。後者はアクティブマトリックス電子源からの1万本の電子ビームで並列描画するもので、「超並列電子ビーム描画装置の開発-集積回路のディジタルファブリケーションを目指して-」東北大学出版会 (2018)(江刺正喜他)として出版された。しかし、この電子ビーム描画装置はきりがないので十数年取り組んで止めた。
6.定年前と定年後:設備開放と知識提供
西澤先生が約半世紀に渡って運営してきた「財団法人 半導体研究振興会」が2008年に閉鎖されることになり、理事で副所長だった私は建物を東北大学に移管して、「西澤潤一記念研究センター」(以降 西澤センター)としてもらった。9,000平米の大きな建物に1,800平米のクリールームがあり、そこに株式会社トーキンのパワートランジスタ工場が移設されていた。職員の再雇用のこともあり、「試作コインランドリ」(http://www.mu-sic.tohoku.ac.jp/coin/index.html)という名前で会社から派遣された人が自分で操作し、試作開発ができるようにした。2010年より戸津健太郎准教授(現在教授)が中心になって運営している。ここで作られたデバイスを市販させてほしいとの要望に応え、東北大学が文部科学省や経済産業省と交渉し、2013年より製品製作が認められた。異常なほど進歩し続ける半導体分野では、装置は更新され古い装置はどんどん捨てられるので会社から貰うことができる。ユーザーはどんどん増えて2024年末まで合計334社に使われ、毎月1,000件ほどで独立採算に近い形で運営されている。会社のニーズに応える仕事も良いと思っている。また建物はモノづくりのスタートアップ企業や、電気自動車を作る学生サークルなど、いろいろな形で使われている。
2013年3月末で、兼務していた工学研究科を定年退職し、「設備共用へのこだわり」という題で最終講義を行った。2016年に本務の「原子分子材料科学高等研究機構(WPI)」を退職し、75歳の現在は株式会社メムス・コアのCTOと東北大学西澤センターのシニアリサーチフェローをしている。株式会社メムス・コアは2001年12月に本間孝治社長が仙台に設立したMEMS開発請負会社で、古い設備で東北大学の「試作コインランドリ」も使い、開発や少量生産でも採算が合う形でやっている。
MEMS技術は様々な知識を必要とするため、いかにして多様な情報にアクセスするかが大きな課題である。教授の時は250回/年ほど会社の相談に乗り、セミナーなどを開催して知識提供に努めてきたが、これを大切にしている。2004年には、産学連携の拠点となる「MEMSパークコンソーシアム」を設立し、各地で無料のMEMS集中講義を毎年開催している。また、1,000冊ほどある文献ファイルを整理しExcelのキーワードで検索できるようにし、工具や部品なども整理して探しやすくしている。展示室(http://www.mu-sic.tohoku.ac.jp/nishizawa/)を5部屋整備し、サンプルなどを見てもらえるようにしている。今の若い人も大学の研究者も分野が狭くなっているが、時間的な流れも含めて幅広く知っていることが大事。そこで、近代技術史について紹介する展示室も整備しており、雑誌への連載記事も書籍として纏めて出版予定である。
日本の企業は、昔は割と基礎から研究をしていたが、グローバル化で基礎からやる余裕がなくなり、研究が実用に繋がらなくなった。ヨーロッパでは、企業と大学の間に公的研究機関が入り、例えばドイツでは、フランフォーファーが、各大学の中に置かれ、大学の研究が完成度をあげて社会に出る仕組みになっている。一方で日本は縦割で、(経産省所管の国研である)産業技術総合研究所(産総研)は、大学とも会社ともほとんど繋がっておらず、ドイツと比べて日本では国研が社会実装に貢献していない。そこで藤井黎仙台市長にドイツに行ってもらい、仙台市とフラウンホーファーで協定を結んだ。2005年からフランフォーファシンポジウムを仙台で毎年開催している。
次世代人材育成も行っている。秋田の中学生に紙風船の研究を教えたり、2007年から早稲田塾(東京)の高校生たちに、ものづくりを教えたりしている。優秀な高校生のチームを台湾や北京大学へ連れて行った。中国でモノづくり大会の優勝者が、任天堂の「スーパーマリオブラザーズ」で、身体に加速度センサを付け自分で飛び跳ねて障害物を飛び越えるゲームのプレゼンを行っていた。これを「国際大会にしませんか」と提案し、MEMSを使ったアプリケーションのアイデアや完成度等を競い合う国際コンテスト「国際ナノ・マイクロアプリケーションコンテスト」(略称iCAN、現「国際イノベーションコンテスト」)が始まった。iCANでは、ヘレン・ケラーのような指文字を音声にする装置や、赤ちゃんのうつ伏せ寝を防止する装置など、MEMSを用いた様々なアプリケーションのアイデアが学生により提案されている。
今の日本では、論文数があまりにも重視され過ぎているので、いつも「“良い子ぶりっ子”(論文数)よりも役に立つ嬉しさを」と話している。そのためには、アウトソーシングせず、ニーズに応えて自分でやること(オンザジョブで成長、分野開拓)、アクセスしやすい情報蓄積整理(質の高い知識提供サービス)、自作装置や古い装置の活用などによる設備共用 (試作品の完成度を高め産業化) が重要になる。
議論のようす(一部抜粋)
Q. ヨーロッパの商談会でMEMSの話をすると、会場からは「エサーシ!」コールが湧きあがる。江刺先生の技術が世界的に評価され素晴らしいことはわかっていたが、今回、設備共有や役に立つことに対する江刺先生のモチベーションを直に感じることができた。研究者として「皆でシェアしていく、役に立つ」精神性はどのような考え方から生まれたものか。
A. 西澤先生がずっと戦ってきた。西澤先生は戦後、日本が食べられない状態を見て何とかしたい、貢献したい思いでやってきた。当時、産学連携は歓迎されなかったため、西澤先生は苦労して戦ってこられた。私の頃はとても恵まれていて、産学連携が推進された頃だったので、とてもやりやすかった。一方で、周りを見ると論文重視で、他でやっていない新しさだけになっている大学の現状を知っていた。そこで、西澤先生と大学の現状を見て、産業化に近い部分もいいんじゃないかなと思ってやってきた。よく「西澤先生幸せ、大見先生不幸」と言ってきた。西澤先生は発展途上で関わったから幸せ、大見忠弘先生は半導体が急速に進歩する時に関わったので、大学ではやりようがない。私が関わったMEMSは発展途上で、西澤先生と同じ考えで「役に立とう」でちょうどよかった。けれども今は、MEMSの世界もやりにくくなっている。成熟化するとやりにくくなるのは何でもそう。
Q. やっとMEMSのことが理解できた。半導体というと何でもお金がかかるが、江刺先生のやり方はお金がかからないという、すごい話。江刺先生のやり方がよいから、大学と産業がつながり、ヨーロッパでは江刺コールが湧き上がるのに、なぜ日本ではヨーロッパのように大学と産業がつながらないのだろうか。
A. ドイツではフラウンホーファーの資金は40%が会社からなので、会社からのニーズが拾われるが、日本の産総研は国のお金がほとんど。昔なら産総研も大学も論文を書くことで価値があった。会社も基礎からやっていたから。けれども今はグローバル化の中で他国に勝たないといけない。昔のやり方のままでは駄目で、組織間の壁を低くする必要がある。
Q. 江刺先生のように産業と連携し「国のお金は要らない」というスタンスでやっていて、それに国が「お金を出すから何とかやって欲しい」という話は美しい。
A. 大臣から「お金を出す」と言われたけど、お断りした。そのための設備を買うと、古くなるし維持費がかかるので、やれるはずがない。それは、この分野に長く関わっていたからわかる。一方で、新しくビジネスをやった人はそれがわからない。我々の分野では2000~2010年頃が酷かった。すごくつまらない技術なのに特許を取ってメーカーに売り込む人がいた。皆あまり知識がなかったので、その話に乗って10社くらいが同じことをやってすべて撤退した。情報不足で、勉強していなかったせい。日本は変わるべきところが多いと思っている。
Q. 江刺先生のビジョンを継承する人は?
A. 戸津教授が活躍している。最近は特に半導体人材育成のニーズが高まっており、会社や学校等から「もっと実習をやってほしい」という要求が増えている。もともと集積回路が得意なので、1970年代の設備で、10 μmピッチ、現在の5000倍の大きさの技術で、一通り成功させて見せるやり方をやろうとしている。そのような意味では、大きなビジネスにも繋がるようになっている。
Q. 江刺先生の話を聞いて、MEMSはこんな身近なところに入っているんだと、びっくりした。江刺先生が作ったMEMSを我々仙台市民も使っているのに、そのことを地元の市民が知らないのは勿体ない。我々の普段の生活の中に、江刺先生がつくったMEMSが埋め込まれていることをもっとPRし、地元の市民に自信を持たせることが重要ではないか。そして市民が「こんなことに困っているんだよね」と先生のところに相談に行き、「こんなことができないか?」と市民のニーズから「これをつくれるのではないか?」と、市民と大学が連携してイノベーションを起こすことが仙台なら可能ではないか。
A. 私はエンジニアリングの端っこで、産業規模から言うと、金額的にはそれほど大きくはない。関係分野の会社には伝わっており、一般の人にさらに伝える必要はあまりないと思っている。地元の誇りにはなるが、それなりに伝わっているのではないか。
Q. 江刺さんが「よい子ぶりっ子より、役に立つ嬉しさを」と仰っているのが、とてもよく伝わってきた。仕事柄、西澤潤一さんを間近に見て、世の中に役に立つことが本当に楽しいことが伝わってきた。江刺さんもその血を引いている。オタクであることを自覚したのはいつ頃で、オタクでよかったと思われたのはなぜ?
A. 昔からラジオづくり等、ものづくりの類が好きだった。割と身体が弱く、普通の人の30%くらいしか赤血球がなくて、マラソン大会でビリになったりしていたので、物理部などで、ものづくりをずっとやってきた。小さな頃から定年後までずっと同じことをやっていて、楽しんでやってきている。大変な思いでやっている人も多いと思うが、私は恵まれていて、西澤先生の真似をしてやってこられたので感謝している。
Q. 競争激しい分野で、メムス・コアがうまく行っている理由は?
A. メムス・コアがうまく行っている理由は、他の会社が潰れたから。MEMSは社会のニーズがあるにも関わらず、中古を使うとか、米国でも大学の設備を借りるとか、それなりの工夫をしないとやっていけない世界。
Q. これまで「失敗した」と思ったことは?
A. なかった。周りの人が戦ってくれた。西澤先生が戦ってくれたが、大学院生の時も研究室の先輩が戦ってくれた。電子回路が集積回路に変わってやりようがなくなった時、先輩が「センサをやりたい」「心電図の自動解読など情報処理をやりたい」と言って、先生と対立し、先生が「学生のやりたいように」と折れた。私も特許の問題の時などは少し戦ったが、とても恵まれた環境でやってこられたので戦わずに済み、サービス精神を旺盛にしてやってこれた。
Q. これから日本をどう変えたらよいだろうか。
A. 現場から議論して広めていけると良いと思う。今回のような機会を上手に活かして、これからやれたら良いのではないか。
宮城の日本酒
ざっくばらんな意見交換を促進することを目的として、季節の限定酒をご用意しました。なお、以下は用意した日本酒の銘柄、造り、使用米、精米歩合、製造年度を示しています。
1.山和星 純米大吟醸 ササニシキ40% 6BY
伯楽星と山和の年に一度のコラボ酒
技術交流を目指し毎年交互の蔵で造られる ササニシの純米大吟醸
今回は伯楽星の新澤醸造店での醸造です
2.伯楽星 純米大吟醸おりがらみ生雪華 雄町40% 6BY
川崎蔵で造られる 年に一度の純米大吟醸生 そのおりがらみ
クラスに注ぐと そのオリが雪の華のようで雪華と命名です
3.乾坤一 純米大吟醸 黒 山田錦40% 5BY
村田町の蔵大沼酒造店 兵庫県産山田錦で造る
販売店限定鑑評会出品用タンクの純米大吟醸
4. ZAO 純米大吟醸 中取り 山田錦40% 5BY
白石の蔵王酒造 特約店販売純米大吟醸 その中取り
5.橘屋 秘傳山廃純米吟醸生原酒 立春小吉 蔵の華50% 6BY
美里町 黄金澤の特約店別ブランド橘屋
生は当店だけの瓶詰めで この時期飲まれる皆様に小さな幸せ 立春小吉
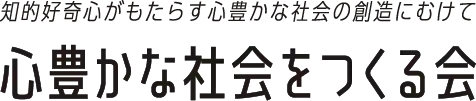


 [略歴](えさし・まさよし)1949年仙台市生まれ。1971年東北大学工学部電子工学科卒。1976年同大学院博士課程修了。同年より東北大学工学部助手、1981年助教授、1990年より教授となり、2013年定年退職。現在 、株式会社メムス・コア CTO兼 東北大学 マイクロシステム融合研究開発センターリサーチフェロー。半導体センサ、マイクロシステム、MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)の研究に従事。主な受賞歴は、日本IBM科学賞(1993)、SSDM Award(2001)、第3回産学官連携推進会議 文部科学大臣賞(2004)、第54回河北文化賞(2005)、紫綬褒章(2006)、IEEE Andrew S.Grove Award (2015)、IEEE Jun-ichi Nishizawa medal (2016)、瑞宝中綬章(2022)等多数。
[略歴](えさし・まさよし)1949年仙台市生まれ。1971年東北大学工学部電子工学科卒。1976年同大学院博士課程修了。同年より東北大学工学部助手、1981年助教授、1990年より教授となり、2013年定年退職。現在 、株式会社メムス・コア CTO兼 東北大学 マイクロシステム融合研究開発センターリサーチフェロー。半導体センサ、マイクロシステム、MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)の研究に従事。主な受賞歴は、日本IBM科学賞(1993)、SSDM Award(2001)、第3回産学官連携推進会議 文部科学大臣賞(2004)、第54回河北文化賞(2005)、紫綬褒章(2006)、IEEE Andrew S.Grove Award (2015)、IEEE Jun-ichi Nishizawa medal (2016)、瑞宝中綬章(2022)等多数。
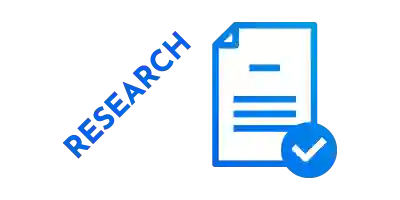
イベント実施報告一覧に戻る