議事録(概要)
ゲストの高田昌樹さんによる講演要旨
「挑戦は、挑戦を呼ぶ:ナノテラスという『意志』の物語」
高田昌樹さん(東北大学副理事(ナノテラス共創担当)・光科学イノベーションセンター理事長)

光科学イノベーションセンター理事長の高田昌樹さん(東北大学副理事(ナノテラス共創担当))は、「挑戦は、挑戦を呼ぶ:ナノテラスという『意志』の物語」と題して講演を行い、次世代放射光施設「ナノテラス」の実現に至るまでの経緯と、その背後にある信念を語りました。
次世代放射光施設「ナノテラス」実現の裏舞台
高田さんはまず、「科学と社会」の関係について言及しました。2003年から兵庫県の大型放射光施設SPring-8で放射光を使った研究を進める中で、社会とどう結びつくのかに疑問を抱いていたと言います。大きな転機となったのが2011年の東日本大震災でした。未曾有の災害を前に科学の役割とは何かを考える中で、「科学の力で復興のエンジンをつくりたい」と決意し、東北放射光施設構想を立ち上げたことが、挑戦の始まりだったと振り返りました。
当初は関西から東北の大学や自治体に働きかけを行っていた高田さんでしたが、東北に骨を埋めて挑戦する覚悟を固め、2015年に理化学研究所を辞して単身仙台へ。しかし反対の声も多く、また、仙台へ移動後、国からの支援を得ることがいったん厳しくなるなど、厳しい船出だったといいます。それでも高田さんは「面白くなりましたね」と前向きに捉え、この危機を、国家プロジェクトに昇華させる契機としたと語りました。ここから誕生したのが、後にナノテラスの中核となる「コアリション(有志連合)」という仕組みです。
高田さんは、資金不足の中で「企業が資金を出すことで社会ニーズの存在が証明される」と考え、放射光を使ったことのない企業でも、学術メンバーと1対1で共創できる体制を構築しました。さらに東北経済連合会と連携し、中小企業も小口で参加できる仕組みを整備。「コアリションという多義的な言葉を使ったのは、すべての関係者が自分事として関わることで、持続的に進化する仕組みにしたかった」と語りました。
資金集めのために自ら約4,000社を訪問。挑戦を重ねる中で共感の輪が広がっていったと言います。そして2018年、国もこの計画に乗り出し、官民地域パートナーシップの下で進められる国家プロジェクトに発展しました。高田さんは「ナノテラスは『誘致』ではなく、被災地の人々が身銭を切ってつくり上げたものだ」と強調し、地域パートナーと企業が建設費380億円のうち約180億円を負担したことに触れ、「だからこそ、その価値を地域に還元する責任がある」と語りました。
「見える」ことが、すべてを変える
ナノテラスとは、太陽の10億倍も明るい光で、ナノの世界を「⾒える化」する道具です。科学の進歩は「見ること」の革新とともにあるとし、DNAのX線写真が二重らせん構造の解明につながり生命科学の扉を開いた例をあげ、「見えることが新しい価値を生む」と述べました。ナノテラスが目指すのは、専門家だけがわかるデータではなく、製品の価値を直感的に理解できる3D映像や画像の形で示すことと言います。
その成果の一例として、宮城県の老舗製麺所・マルニ食品との共同研究を紹介しました。放射光を使って麺の内部構造を可視化し、長年の課題だった食感改善を実現した結果、フリーズドライ麺の品質向上に成功。当初は放射光に戸惑っていた同社の社長も、今ではナノテラスを事業戦略の柱に位置づけているといいます。「ナノテラスに麺を入れると美味しくなるらしい」という地域の声も、「それはナノテラスが自分たちの課題解決の場として地域から理解された証拠」と高田さんは微笑みます。この事例は「経営者⾃⾝がその可能性に覚醒し、挑戦を知の拠点が⽀える、理想的な産学共創の姿」と言います。
挑戦は、予測しない挑戦を呼ぶ
さらに、企業の課題解決が新たな発見を生んだ事例も紹介されました。大手化学メーカーからの要望で、東大・原田教授との共同研究により、ポリマー表面の水分子構造を解析した結果、たんぱく質の付着を防ぐ原理を発見。これが後にコロナ禍で重症患者に使われる医療用コーティング材に応用されました。
また、今年のノーベル化学賞を受賞した北川進さんとの共同研究についても触れ、「当初は放射光と無縁だった研究者がノーベル賞を受賞したように、農業からノーベル賞が生まれてもいい」と語り、高校生や文系の若者にも科学に触れてほしいと呼びかけました。
質疑応答では、データの活用、人材育成、行政との連携、経済効果などが議論されました。高田さんは「企業と大学が1対1で製品化まで責任を持つ仕組みが重要」と述べ、生成AIを活用した産学マッチングなど新たな挑戦も進めていることも紹介しました。また、高校生向けに行っているナノテラスの授業を単発イベントで終わらせず、カリキュラム化・予算化して継続する重要性も指摘しました。ナノテラスを単なる研究施設でなく、多様な人々が⾃分事として関わり、共に答えを創り続けていく、その終わりのない価値創造の連鎖が日本の未来を切り拓く鍵であるとの信念が語られました。

議論の様子(一部抜粋)
Q1 東北に企業や人材を呼び込むには、ハード面の整備だけでなく、データを如何に企業の現場で活用できるかが重要。予算が毎年削られる中、経済効果が認められなければ、基礎研究に配分される予算もない。経済効果に如何に繋げられるかが重要(文部科学省から出向中の大学関係者)。
A1 単にハードをつくるだけでなく、ナノテラスを日本のインフラとして活用するために「コアリション」の仕組みを構築した。オープン・サイエンスはよい考え方だが、競争領域で企業とアカデミアが1対1で責任を持って製品化まで到達できなければ、企業は資金を出さない。地域も主体的に関わり、ユーザーではなくパートナーとして協働する、世界初の試みが進行中であり、大学・企業・金融・スタートアップをつなぐイノベーション・エコシステムが構築されつつある。
Q2 今後データの活用が益々重要になる一方で、データを活用できる人材の不足が大きな課題(大学関係者)。
A2 若者を如何に巻き込めるか。これからはデータが経済を動かす時代。コアリションを通じて、その意識を醸成したい。挑戦の場ができれば、皆、新しいことを考える。例えば、生成AIを活用した企業ニーズとアカデミアのマッチングを新たに始めている。高専や異分野からの参画など、多様なバックグラウンドの人が集まる場づくりが大切。
Q3 ナノテラスでの研究が事業につながる世界初の仕組みであり、世界中から東北に人が集まる可能性を感じた。その本質を行政は理解しているのだろうか(市民)。
A3 最初は「本当に企業から資金が集まるのか」と戸惑っていた行政職員も今では一緒に走ってくれている。仙台市や宮城県が放射光のトライアルユース事業を実施していることも、理解が深まった証拠。地域の人々が主体的にナノテラスの活用を考えるようになることが、コアリションの目指すところ。
Q4 新たなメイドインジャパンの萌芽がナノテラスから生まれる可能性を感じた。行政も含めて、メイドインジャパンの再興を目標にすべき(議員)。
A4 高校生向けのナノテラスの授業はイベントでは終わらせず、カリキュラム化・予算化して継続的な教育プログラムにしてほしい。そうして初めて地域の特色ある学びが生まれる。震災を経験した宮城の高校生は意識が高く、講演中も真剣そのもので、広島の被爆後の復興に重なる強い精神を感じた。こうした若者が地域を牽引していくと期待しており、大人が仕組みを整えることが重要だ。また、放射光研究の応用は農業や水産業にも広がっており、例えば、米に含まれる元素や土壌・水質との関係を分析することで、地域産物の特性を科学的に捉えられる事例も生まれている。知恵を結集できる場として世界一になれる可能性を秘めている。
宮城の日本酒
ざっくばらんな意見交換を促進することを目的として、季節の限定酒をご用意しました。なお、以下は用意した日本酒の銘柄、造り、使用米、精米歩合、製造年度を示しています。
1.伯楽星 純米大吟醸 東条秋津山田錦 山田錦29% 6BY
三本木 新澤醸造店 三年連続 世界酒蔵ランキング第一位
2.宮寒梅 純米大吟醸 醇麗純香 ひより・美山錦35% 6BY
大崎市 寒梅酒造 全国新酒鑑評会出品酒 特約店酒
3.墨廼江 純米大吟醸 谷風 山田錦40% 6BY
石巻市 墨廼江酒造 宮城の横綱谷風命名 年二回の限定酒
4.日輪田 生モト純米大吟醸 雄町45% 5BY
栗原市 萩野酒造 過去IWC純米大吟醸の部最高金賞受賞
5.あたごのまつ 純米大吟醸 白鶴錦 白鶴錦50% 6BY
三本木 新澤醸造店 白鶴開発米で造る 食中純米大吟醸
6.メガネ専用 米非公開60% 6BY
栗原市 萩野酒造 10月1日 日本酒の日のアピール酒
日本酒を飲んだことのない方にも手に取って飲んでもらいたい想いから10年前から
この時期に販売 たまたまその日は1001メガネの日でもあった
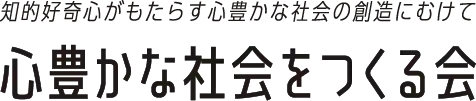


 【ゲスト】高田昌樹さん(東北大学副理事(ナノテラス共創担当)・光科学イノベーションセンター理事長)
【ゲスト】高田昌樹さん(東北大学副理事(ナノテラス共創担当)・光科学イノベーションセンター理事長)
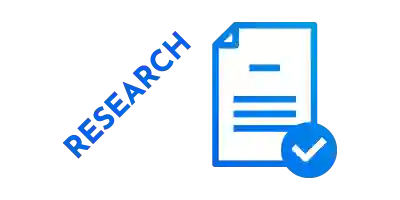
イベント実施報告一覧に戻る