令和6年第4回定例会 12月16日
本会議
心豊かな社会をつくる会 大草よしえ
仙台市DX推進計画の進捗状況

心豊かな社会をつくる会の大草よしえです。議長のお許しをいただきましたので、私からは仙台市DX推進計画について一般質問を行います。
人口減少と少子高齢化が進む中、行政サービスの効率化と住民の利便性向上の両立が喫緊の課題となっています。その解決の鍵として、デジタル技術を活用し、よりよい組織、よりよい社会へと変革していくデジタル・トランスフォーメーション(DX)が今、自治体にも求められています。
本市においても、これまでのICT利活用等の取組みをベースに、今年度からの3か年を「集中改革期間」と位置づけたDX推進計画がスタートしました。さらに本議会としても昨年度から新たにDX推進調査特別委員会が立ち上がり、私も委員として1年間勉強させていただきました。そこで今回は、これまでの1年間の調査研究と現場からの声をもとに、本市DX推進計画の進捗状況について確認を行っていきたいと思います。
◆ 本市DXの将来像「フルデジタルの市役所」
本市が目指すのは、単なるデジタル化にはとどまらない、『「ひと」と市役所の「かかわり」の変革』であると、DX推進計画の中で掲げられています。その成果として生み出されるリソースは、「ひと」にしかできない業務に割り当てることで、多様な接点をもった「ひと」中心の行政サービスを目指す。これが本市DXの将来像として掲げる「フルデジタルの市役所」であると、この計画では定められています。
計画そのものについては、私が自治体DXについて一年間勉強した限りではありますが、ビジョンとその具現化までのプロセスが非常に明確で、よく練られた計画と認識しております。しかしながら、計画がいくら素晴らしくとも、それが本当に実現できているか、最終的に確認する仕組みが適切に運用されていなければ、「絵に描いた餅」になりかねません。
そこで、本計画のKPIは主に3つ設定されているとのことですので、この3つのKPIに沿って重点取組み事項の進捗状況を確認していきたいと思います。
(1)重点取組み事項1「手続きのオンライン化」
まず、1点目の重点取組み事項として掲げられている「書かない」窓口、「行かない」窓口サービスの充実について確認します。KPIとしては令和8年度までに「年間に受け付ける業務476万件のうち、約9割を占める上位100手続きのオンライン化」と設定されていますが、現在の進捗状況は如何でしょうか。伺います。
さらに、この「手続きのオンライン化」については「進捗状況を随時、ホームページ等でわかりやすく公表し、市民の意見等を取り入れながら柔軟にオンライン化を進める」と計画では掲げられています。市民をはじめ、多様なステークホルダーを当事者として巻き込みながら、多様な価値を評価に反映し、タイムリーにPDCAを回して改善を繰り返していくプロセスは、ユーザー視点に立ったDXを推進していく上で非常に重要と考えます。そこで、このフィードバック機構が実際に機能しているかを確かめるために、その公表状況について、確認を行いました。
まず、本市ホームページの「DX・デジタル化に関する取組み」のページには、「DX推進計画」の次に、「デジタル改善目安箱サジェストセンダイ」があります。確認したところ、市民から現在200件近くの情報が寄せられ、その受付状況と対応方針が比較的タイムリーに更新されており、計画通りに進んでいるように見えました。

ところが、その次にある「オンラインで可能な手続」をクリックすると、PDFで公表されていること自体は確認できましたが、PDFには手続名と担当局と運用方法の一覧が単にあるだけで、リンクでは飛べず、確認しようと思っても、直接確認できない仕様になっていました。なぜ「オンラインで可能な手続」にリンクで直接飛べない仕様になっているのでしょうか。この公表の仕方では行政がやったことの一方的なPRだけで、逆に、「市民の意見等は柔軟に取り入れたくない」というスタンスにすら、見えてしまうのではないでしょうか。市民等が直接確認できる仕様に改善すべきと考えますが、担当局のご所見を伺います。
さらに、この「オンラインで可能な手続」と公表されている手続が、実際にオンライン化されているかも、当方で確認したところ、既に「Eメールで手続可能」と公表されているにもかかわらず、提出先はFAXか郵送のみで、メールアドレスの記載がない手続きが、複数件、確認されました。既に「Eメールで手続可能」と公表されているにもかかわらず、このような実情があることは、非常に問題と考えますが、担当局のご所見を伺えますでしょうか。
(2)重点取組み事項2「業務・職場のデジタルシフト」
次に、2点目の重点取組み事項に掲げられている「業務・職場のデジタルシフト」について確認します。KPIとしては令和8年度までに「業務に用いる印刷用紙の購入量50%減」が設定されていますが、現在の進捗状況は如何でしょうか。伺います。
(3)重点取り組み事項3「DX人材の確保・育成」
続けて、3点目の重点取組み事項として掲げられている「DX人材の確保・育成」について確認を行います。KPIとしては令和8年度までに「業務改革(BPR)プロジェクト研修を120名以上、デジタルリテラシー向上研修を1,200名に実施」と設定されています。
このKPIの進捗状況に加えて、DX人材育成の計画にある「職員の意識改革・意欲向上:DX推進マインドの醸成」の進捗状況についても伺えますでしょうか。前回のDX調査特別委員会でも「職員の挑戦を促し、その挑戦を評価する環境整備が必要」との意見が複数の委員からあげられましたが、そのような環境整備は進んでいるでしょうか。併せて伺います。
(4)DX推進のハードル
人材育成に関して、デジタルリテラシーのみならず、DXマインド醸成の進捗状況について、このように確認を行う理由は何かというと、私が一年間、自治体DXについて調査研究を進め、現場からの声を聞く中で、DX推進で最も高いハードルとなっているのは、実はテクノロジーの方ではなく、むしろ人の“心の壁”の方ではないか、と痛感したためです。
そう痛感したきっかけは、実は市民の方からの要望で、「デジタルがもう当たり前になった時代に、役所と電話や郵送でやり取りするのは、とても非効率で、負担感が大きいので、せめて区役所のホームページにメールアドレスを併記してほしい」という要望を頂戴したことがきっかけでした。そこで、DX推進担当のまちづくり政策局を通じて、関係する局や区役所とやり取りを行い、結果的には掲載いただけたのですが、外から見ると簡単そうに見えることですら、内部では色々と整理や調整が必要なことがわかり、DXは一筋縄では進まないことを痛感した次第です。
そもそも人間は、新しいものに対しては基本的には保守的で、何か“必然性”がない限り、その壁をわざわざ乗り越えようとは思わないものです。DXについても同じで、DXを自分ごととして捉えるかどうかは、その人の個性や環境要因によって、かなり濃淡があることも、現場への様々なヒアリングを通じて、改めて実感しました。このように“必然性”の濃淡がある中で、組織としてのコンセンサスを取ることは、決して容易なことではありません。過渡期の今、この“必然性”を如何に共有できるかが、本計画で掲げる「集中改革」成功の要になるものと考えます。
そこで、この“必然性”を共有するために、可能性を見い出せる取組みとして、私は本市主催の自治体向けDX展示会「TOHOKU DX GATEWAY」にぜひ注目したいと思います。

本イベントは、約120の自治体・企業等の優良DX事例を紹介し、横展開を図ることで、今後より厳しい行財政運営が想定される中でも、東北地域全体の自治体DXを進め、持続可能な行政サービスにつなげることを目指すもので、12月上旬に仙台国際センターの展示棟を借り切り、本市が昨年度から主催しているイベントです。単なるDXの事例紹介にとどまらず、実際に導入した自治体職員の生の声を聞くことができる点が、他にはない特徴とのことで、基調講演者やパネリストからも「規模・内容ともに首都圏並みか、それ以上」と、高い評価を得ていました。
私も昨年に続き今年も、朝の基調講演から午後のパネルディスカッション、ブース展示まで、丸一日参加させていただきましたが、本市の目指す『「ひと」と市役所の「かかわり」を変革するDX』とはこういうことなんだと、ワクワクしながら実感できる、非常によいイベントだったと思います。郡市長も、最初の挨拶だけでなくパネルディスカッションを最後までご覧になっており、登壇者の方も「市長が最後まで聞いているのは珍しい」と驚いておられました。それくらい、本市として力を入れているイベントかと存じます。
そこで提案ですが、せっかく本市が力を入れて主催しているこの「TOHOKU DX GATEWAY」を、東北や全国への発信はもとより、足元の本市DX人材育成計画の「意識改革・意欲向上:DX推進マインドの醸成」に積極的に活用されてみては如何でしょうか。DX推進でハードルとなっている“心の壁”を乗り越えるきっかけとして、本イベントは高いポテンシャルを有していると、私は感じております。
「集中改革期間」と位置付ける本DX推進計画も、残すところ、あと2年3ヶ月となりました。引き続き、この計画に基づき、私も進捗状況を確認して参りたいと存じます。最後に、郡市長に本市DXの今後にむけた意気込みをお伺いして、私からの一般質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。
答弁 Answer
市長答弁
只今の大草よしえ議員の質問にお答えいたします。TOHOKU DX GATEWAY と、本市のDXに向けた意気込みについてお答えいたします。TOHOKU DX GATEWAY は、出展者を含めおよそ1,800 名、このうち本市職員からはおよそ300 名が参加をいたしました。私自身もブースを拝見する中で出展者の課題解決に向けた熱意というものを実感したほか、ステージイベントでは、デジタル庁や総務省などの登壇者から、人口減少社会に対応した行政サービスの変革の重要性や、国また他の自治体とのシステム・人材の共有化が鍵となることなど、最新の動向を交えてお話をいただいたところでございます。本市職員を含む多くの参加者にとって大きな刺激となり、そして意識改革と意欲の向上に繋がる有意義なイベントになったものとそう認識しております。今後とも、課題先進地である東北を牽引するという本市の役割も踏まえながら、地域におけるDXの加速化に資するよう、力を尽くしてまいります。
まちづくり政策局長
はじめに、手続きのオンライン化の進捗状況についてお答えを申し上げます。DX推進計画では、年間受付件数上位100 手続きのオンライン化を令和8年度までに実施することとしております。この間、37 手続きがオンライン化されており、残る63 手続きにつきまして、今年度各手続き所管課にヒアリングを行い、連携して課題を整理するとともに、具体的な作業計画を策定いたしました。現時点までに、介護保険の認定申請や保育施設等の利用申請など8手続きを新たにオンライン化しており、残る55 手続きにつきましても、令和8年度末というゴールを見据えながら進捗管理を行い、関係局との連携のもと、確実な取組みを進めてまいります。
次に、オンライン化した手続きの公表に関するお尋ねでございます。現在、オンライン化した手続きにつきましては、ホームページ上で、一覧表により分野別に手続き名称、担当局、手続き手法を掲載しておりますが、ご指摘の通り、個別の手続きへのリンクはない状況でございます。今後、このページにおきましても、個々の手続きへのリンクを貼るほか、掲載内容を追加するなど、市民の皆様の利便性に配慮した見直しに努めてまいります。
次に、オンライン手続きの案内についてのお尋ねでございます。オンライン化した手続きは、本市のホームページにおきまして、各所管部局がそれぞれの手続きを案内するページを設けておりますが、掲載内容に関する共通の方針を設けていないこともあって、特定の事業者を対象とする手続きなどの場合に、メールアドレスを記載していない例もあるものと承知しております。今後、オンライン手続きの案内がわかりやすい内容となりますように、外部の専門家にもご意見を伺いながら、共通した方針を策定するなど、関係部局と連携して改善に努めてまいります。
次に、ペーパーレス推進の進捗状況に関するお尋ねにお答えいたします。DX推進計画では、令和8年度までに、業務に用いる印刷用紙の購入量を令和4年度比で50%削減するという目標を掲げております。今年度、資料の電子化や電子決裁の活用などの具体例を示した通知を全庁に発出するとともに、デジタル戦略推進部内において庁内LAN 端末のモバイル化を先行実施し実際に検証したところ、11 月までに、紙使用量を概ね50%減少させることができました。来年度には、順次、全庁にモバイル端末を導入してまいります。このような検証結果の共有も図りながら、ペーパーレスの推進に努めてまいる考えでございます。
次に、DX人材育成の進捗状況などに関するお尋ねにお答えいたします。DX推進計画では、人材育成にかかる目標として、令和8年度までに、デジタルリテラシー向上研修受講者を1,200 名以上、BPRプロジェクト研修受講者を120 名以上と掲げております。現在、デジタルリテラシー向上研修は約900 名、BPRプロジェクト研修は37 名が受講しており、今年度から開始した経験年数や職位に応じたDX研修には、約850 名が参加したほか、様々なデジタル技術を体験できるデジタル見本市など、意識改革・意欲向上への取り組みを進めております。この間、職員の挑戦を促す取り組みとして、若手職員を中心とした窓口改善や、デジタル活用に関する意見提案なども実施してきたところでございまして、今後とも、こうした取り組みにより、職員のスキルや意欲の向上を図りながら、デジタル人材の育成に努めてまいりたいと存じます。
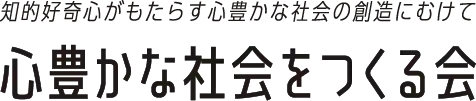


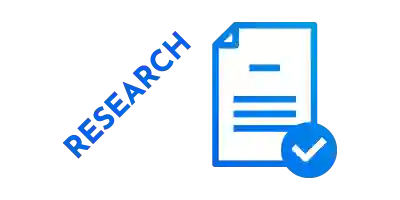
活動報告一覧に戻る