令和7年第1回定例会 2月18日
本会議(一般質問)
心豊かな社会をつくる会 大草よしえ
令和7年度施政方針『イノベーションにあふれる』まちづくり
心豊かな社会をつくる会の大草よしえです。議長のお許しをいただきましたので、私からは、今年度の施政方針で郡市長が掲げられた「多様な発想が掛け合わされ、イノベーションにあふれる」まちづくりのうち、「イノベーション」の観点から一般質問を行います。
そもそもイノベーションとは、イノベーションの提唱者として、21世紀前半に活躍し、100年以上経った今、再び注目を集めているオーストリアの経済学者・シュンペーター氏の定義によると、イノベーションとは「ものごとの『新結合』『新機軸』『新しい切り口』『新しい捉え方』『新しい活用法』を創造することにより、新たな価値を生み出し、社会的に大きな変化を起こすこと」と定義されています。そして、イノベーションこそが、資本主義経済の発展の原動力であるとされ、イノベーションは経済成長・国際競争力の維持に不可欠です。
本市の10ヶ年の総合計画においても「人口減少などの課題を抱える東北の現状を新たなイノベーションを生むチャンスと捉え、未来を描く必要がある」として、重点施策の目標に「世界に発信できる東北発のイノベーションを生み出す」ことが掲げられています。
(1)ジェンダード・イノベーション
イノベーションの観点から郡市長の施政方針を確認いたしますと、今年度は「イノベーション」という言葉が明示的なキーワードとして登場したのは、「ジェンダード・イノベーション」のみでした。これは、これまでの計画にはなかった、初めて登場した言葉ですので、まずは、「ジェンダード・イノベーション」について伺いたいと思います。
施政方針の中で、ジェンダード・イノベーションとは、「性別、年齢などの『ちがい』を新たな技術開発やサービスにつなげる」と規定しています。本市の10ヶ年の総合計画の序文に掲げられている「一人ひとりが持つ多様な価値観や経験を結集し、都市の活力に変えていくため」のアプローチのひとつとして、導入をお考えのものと推察しております。
もともとジェンダード・イノベーションが提唱された背景は、科学の研究データの被験者が、主に男性やオスのマウスに偏っていたために、その分析結果をもとに、製品やサービスを開発してきたことで、問題が起こっていた弊害が始まりでした。
その事実に着目し、むしろ研究や開発のプロセスに、積極的に性差分析を組み込んでいくことで、イノベーションを実現しようという考え方が、ジェンダード・イノベーションです。
この概念は、2005年に米国スタンフォード大学のロンダ・シービンガー教授によって提唱された比較的新しい考え方で、背景として、研究や開発の現場に、女性が少なかったことが、研究開発の結果に影響を及ぼしたことが指摘されています。
典型例として有名なのが自動車のシートベルトで、男性型のダミー人形を衝突試験で用いるために、女性の負傷率が男性より47%高いというデータがあります。反対に性差に対する無意識の思い込みによって、男性側がデメリットを被る事例もあります。
さらに最近ではニュースでも報道されている通り、AIの学習データやアルゴリズムに、性別のみならず人種などの偏りがあることで起こる弊害も、報告されているところです。
一方で近年では、主にヘルスケア業界で、この性差分析に着目することによって新たな市場が生まれるなど、これまで無自覚だった「ちがい」を分析し、ポジティブな資源へと変える発想が、イノベーション創発の糸口として期待されていることは、承知をしております。
ただし、それまで無自覚だったわけですから、無自覚のバイアスを自覚すること自体が、まずもって簡単なことではありません。
仮に無自覚のバイアスを自覚できたとしても、さらにそこからその次のステップとして、これまで存在していなかった新たな価値を社会に生み出し、そこから社会的に大きな変化を起こす、イノベーション創出までのステップには、さらにいくつもの障壁が存在しています。
今年度の施政方針では「ジェンダード・イノベーションに取り組む」とありますが、そもそも行政として、何を目的に誰に対して何に取り組み、最終的にどのような状態を短期的かつ中長期なゴールと設定して、進めていこうとお考えでしょうか、伺います。
もちろん、新しい取り組みということですので、実現までのプロセスには試行錯誤もあるかとは存じますが、施政方針として掲げている以上、方針はあって然るべきと存じます。本市として、ジェンダード・イノベーションという概念を何に適用することで、何をどのような状態に変えていこうとお考えでしょうか。現時点でお考えの方針をお示しください。
(2)総合計画に基づく重点施策の継続性について
次に、引き続き、「イノベーション」の観点から、総合計画に掲げられている重点施策の継続性について確認をさせていただきたいと思います。
これからの将来、尚一層、何が新たな価値の創造につながるのかの予測は困難となる中、イノベーションに取り組む多様な主体を、産学官民一体となり、長期スパンで持続的に支援する環境を整備していくことは、ますます求められています。
改めて、イノベーションというキーワードを切り口に、郡市長の掲げられている施政方針を確認しますと、今年度は、先程取り上げた通り「ジェンダード・イノベーション」のみがキーワードとしては明示的に登場した他、イノベーションの担い手であるスタートアップについては若者活躍支援の文脈で言及があった一方で、昨年度までは掲げられていた「教育・研究機関の集積を活用し、最先端のリサーチコンプレックス形成に向け企業誘致を進め、産学官協働によるイノベーション創出の基盤づくりを推進する」ことに関する言及は、今年度、特にございませんでした。
特に今年度の施政方針で言及がないというのは、つまり、当初の目標が想定通りに達成された、と評価したということでしょうか。それとも、重要度が相対的に下がり、ジェンダード・イノベーションへと重点が切り替わったということでしょうか。あるいは、「引き続き重点的に取り組むことに変わりはない」という認識で問題ないのでしょうか。伺います。
本市の総合計画にも記載がある通り、東北地域は他地域より先んじて人口減少が進行する中、東北地域の支えによって成り立っている本市の経済も含め、地域経済の縮小が懸念される、厳しい状況の中にあります。
その現状認識を踏まえ、東北経済の持続的な成長を実現するためには、本市が東北全体の経済成長を牽引する役割を担うのだ、という都市像が、計画の中では描かれています。
その理念をもって、「イノベーション創出の基盤づくり」の一環として、例えば、次世代放射光施設「ナノテラス」の補助支援対象を、仙台市内の企業等のみならず、東北地域を中心に日本国内まで拡大し、担当局が中心となって精力的に営業活動を展開していることは承知をしております。
しかしながら、本市が仙台市のみならず仙台市外の企業まで支援していることの認知度は、まだまだ低い、との声が聞かれております。
一方で、そのような本市の取り組みを知った方からは、「仙台市は非常によい取り組みを行っているので、経済団体としても、ぜひ協力したい。仙台市が何でも自前で1からつくる発想だけでなく、東北全体で連携して取り組もう」とのお申し出も受けております。
その連携のお申し出を受けたことは、すでに当局にお伝えをしておりますので、そのような連携の輪を広げていくことで、限られたマンパワーの中で効果的に成果をあげていただくことを望んでおります。
「イノベーション創出の基盤づくり」は、数年スパンで達成されるようなものではなく、長期スパンで、地域一体となって、粘り強く取り組むことによって、初めて成果につながり得るものと認識しております。
これまでも、ここ仙台では、一世紀以上にわたって産学官民一体となって「世界に発信できる東北発のイノベーション」を生み出し続けてきた結果、「学都」という本市の都市個性が磨かれ、今日における若者の流入やスタートアップの輩出、さらに昨年の東北大学の国際卓越研究大学採択などの結果につながっています。
本市が「イノベーションにあふれる」まちになるためにも、これからも「イノベーション創出の基盤づくり」に東北地域一体となって取り組み、多様な人々がイノベーションに挑戦できる環境整備を、ぜひ継続的に行っていただくことを心より期待いたしまして、私からの質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。
答弁 Answer
市長答弁
只今の大草よしえ議員の質問にお答えいたします。ジェンダード・イノベーションについてのお尋ねでございます。
イノベーションの創出には、多様な人材の知識等の掛け合わせで、新たな価値を生み出すことが必要なものというふうに認識をしております。その実践として、ジェンダード・イノベーションに取組むということを掲げたものでございまして、本市においても、昨年、ご紹介のあった、スタンフォード大学のシービンガー教授を招聘してワークショップを開催いたしました。子育てや防災などの分野で新たなサービスの提案がなされて、様々な地域課題の解決の可能性が示されたところでございます。
今後、東北大学や企業などと進めるスマートフロンティア協議会において、参画企業の状況なども踏まえながら、知識の共有や製品、また、サービスの検討を進め、産学官の共創による仙台発のイノベーション創出を目指してまいりたいと考えております。
経済局長答弁
地域経済の持続的な発展を図るためには、東北大学やナノテラスなど、学都の知的資源を生かしたイノベーション創出が重要と認識し、その推進に向けて取組んでまいりました。
そうした取組みを継続することが肝要であり、新年度は、スタートアップ・エコシステムのより一層のグローバル化や、研究開発拠点の集積に向けたウェットラボ整備モデル事業等、新たな施策も展開いたします。
引き続き、関係機関と連携しながら、世界最先端のリサーチコンプレックス形成に向けて、着実に取り組んでまいりたいと存じます。
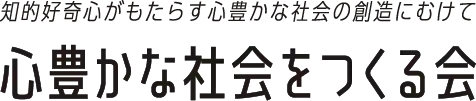


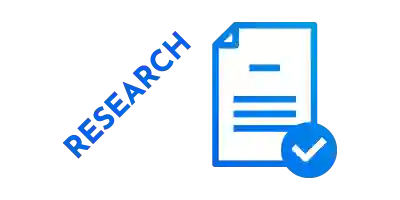
活動報告一覧に戻る