令和7年第2回定例会 6月18日
本会議(一般質問)
心豊かな社会をつくる会 大草よしえ
「グローバル・スタートアップ都市・仙台」
(仙台である必然性の醸成を)
心豊かな社会をつくる会の大草よしえです。私からは、本市のスタートアップ支援に関連して伺います。
本市では、スタートアップを「経済成長のエンジン」と位置付け、スタートアップ支援を推進しています。2023年度からはスタートアップ支援課を新設し、人員・予算ともに大幅に増強して体制を強化。さらに今年度は施政方針で郡市長が「グローバル・スタートアップ都市・仙台」を掲げ、「起業から海外での活躍までシームレスに支援する」と方針を示し、関連予算も16.4億円へ大幅に増強しています。
そして今月4日、内閣府が進める第2期スタートアップ・エコシステムの「グローバル拠点都市」に、本市を中心とした仙台・東北のコンソーシアムが選定されたと発表がありました。東京や関西など全国8つの「グローバル拠点都市」として選定されたことから、これまで本市や関係機関が推進してきた成果と、今回新たに掲げた「世界とシームレスに繋がり」「スタートアップの成長を徹底支援する」積極的なビジョンが、内閣府からも高く評価されたものと認識しています。
ここで改めて、もともとの本市スタートアップ支援の目的に立ち返って考えてみたいと思います。この施策のベースとなる「仙台スタートアップ戦略」では、本市がスタートアップを支援する目的として、「地域経済の雇用の創出や税収の増加」という経済効果を掲げています。しかしながら今回の計画を一通り確認し、関係者にヒアリングを行った結果、本市のスタートアップの成長を支援し、世界につなげるメニューは充実しているものの、その支援メニューは果たして当初の目的である地域の経済効果を達成できるのかと重大な懸念を感じた次第です。
一般論ですが、そもそも企業は経済合理性に基づき、よりよい条件を求めて、日本に限らず世界各地を、企業の都合がよいように移動していくものです。スタートアップも例外ではありません。つまり、たとえ、仙台市が取り組む支援メニューや条件がよく、一時、仙台でスタートアップ数が増加したとしても、他によりよい条件があれば、企業はそこへ移っていくのが、正しい経営判断であり、仙台市にそれを止める権限はありません。そうなれば、企業に居続けてもらうためには、仙台市は他の都市よりも、よりよい好条件を絶えず出し続けなければならないことになってしまいます。これは、ある種の「チキンレース」にさらされることを意味し、それを勝ち抜ける保証はどこにもありません。
「スタートアップ・エコシステム」を真にこの地で根付かせるために必要なもの
では、終わりなきチキンレースにさらされず、ここ仙台に残る、あるいは外部に一度流出した成功者の再流入を増やすためには、一体何が必要かを考えると、単純な条件面だけでない、その土地で事業を続けていく必然性が、必ず必要ではないでしょうか。そして、それは何かと言えば、つまり、郷土愛や地域に対する誇り、そして、地域に貢献しようと思う自負心、つまりは「仙台だからこそ自分は頑張りたい」と思う必然性こそが、単純な条件面を超えて、何よりの内発的モチベーションになるのではないでしょうか。
それは、これまでの歴史を紐解いてみてもそうでした。本市10か年の基本計画の目標には「世界に発信できる東北発のイノベーションを生み出す」とありますが、これは、これまで何もなかったゼロから生み出す、ということではなく、百年以上も前から、ここ仙台から世界を変えるイノベーションが次々と生み出され、地域経済に大きく寄与してきた歴史の積み重ねがあります。そしてそれは、地域に対する誇り、地域に貢献しようという自負心なしには、決してなされないものでした。
その礎となったのが、本市名誉市民でもある本多光太郎博士です。本多博士は1916年、当時世界最強だった永久磁石「KS鋼」を発明し世界の金属工学をリードしたことで世界的に知られる研究者ですが、学術の世界のみにとどまらず、域外の企業を呼び込み、東北大学の研究シーズを事業化する新会社の設立を次々と促しました。今で言う、「大学発ベンチャー」の先駆けです。
その一つ、東北特殊鋼(1936年)の初代社長は九州の実業家ですが、技術指導を仰いだ本多博士から「工場を仙台に設けるなら全面的に指導できる。それが、社会に貢献すること洵に大なり」との提言を受け、「仙台の地に産業を興したい」との想いが重なり、仙台での会社設立に至ったエピソードが残されています。
さらに、地域の学術や産業の発展に大きく寄与したのが、「斉藤報恩会」という仙台にあった財団です。地元の資本家が「国のためになる学問を、己の住む東北の地から生み出そう」と巨額な寄付を投じたおかげで、仙台から文明の先頭に立つ発明や発見が次々と生まれ、数々の企業の設立や成長につながりました。歴史上、今で言う「産学連携」の第一次ブームは、戦前の仙台で開花し、その考え方や実行力は、当時の日本の最先端、世界の最前列に立っていたと言われています。
戦後の企業誘致で有名な例は、ソニーです。今や「世界のソニー」も、創立間もない頃、東北大学の永井健三博士が発明した磁気テープレコーダーの特許が大飛躍の突破口となりました。その縁から、ソニーが永井博士の弟子に「工場を日本の好きなところにつくっていいから、工場長になってほしい」と頼み、弟子が東北大学に近い仙台圏を提案して、1954年、仙台工場が稼働しました。ソニーにとっては初の地方工場、宮城県にとっては初の企業誘致、第一号です。そしてソニーを皮切りに、大手の電機・精密機器メーカーの産業集積が進みました。他にも、本日は時間の関係で取り上げませんが、同様の例は多々あると聞いております。
そして現在、青葉山で次世代放射光施設「ナノテラス」を核に形成が進められているリサーチ・コンプレックスも、1986 年、東北大学の教授達が中心となって地域の産学官を巻き込み、一大ムーブメントを起こした「東北インテリジェント・コスモス構想」の上に実現されたものです。日本が後追い型から脱し、「地域イノベーション・システムの構築」による独創によって、東北から世界へ、スタートアップやイノベーションを生み出そうという戦略は、当時の日本としては非常に画期的な構想でした。しかし、この構想は決して新奇な構想ではなく、むしろ、東北の歴史を発掘する中から過去の遺産を現代に甦らせ、それらを未来へ繋ぐ道筋をつけたものだったといいます。
その中心人物の一人が、「ミスター半導体」「光通信の生みの親」と呼ばれ、本市の名誉市民でもある西澤潤一博士です。私も西澤先生のご自宅に過去、何度も伺って、インタビューさせていただきました。いつも西澤先生は、現在のやり方が過去どの先人によって、どのようにもたらされ、それが現在の伝統や文化にどう繋がっているかを教えてくださいました。西澤先生はいつも「それをちゃんと自覚していないと良い仕事はできない」「先輩だって良い仕事をしてきたのだ。我々だってやればできるのだ、と思わないといけない」と常に強調されていたことが、私の心にも刻まれています。
歴史は、単なる過去の振り返りではありません。わたしたちが、これからの未来をつくる上で必要な地図です。その地域に対する誇り、地域に貢献しようという自負心に裏付けられた歴史こそが、本市のアイデンティティであり、それを世代を超えて引き継いでいくことが、これから、バックグラウンドの異なる多様な人々とも協力し合いながら、ともに、新たな未来をつくる上でも必要な地図になると考えます。そこで伺います。
質問
Q1 グローバル・スタートアップ・エコシステムを、真にこの地で根付かせるためには、その土壌として、地域に対する誇りや地域に貢献しようと思う自負心、つまり、仙台である必然性を醸成することが必要と考えますが、この観点について、まずは市長のご認識を伺います。
Q2 また、仙台を舞台にした先駆的な産学連携の歴史を、本市のアイデンティティとして、ストーリーとして内外へ発信していくことは、「世界に発信できる東北発のイノベーション創出」の実現にむけて、域外から様々な資本を呼び込み、ともに未来を創っていく観点からも、本市の強みになると考えますが、ご所見を伺います。
とはいえ、地域に対する誇り、地域に貢献しようという自負心に裏付けられた歴史を、世代を超えて引き継ぎ、地域に文化として根付かせていくためは、息の長い取り組みが必要です。しかしながら本市からは、それを世代を超えて引き継ごうという気概が、大変残念ながら、感じられません。
その象徴的な例が、本市名誉市民の扱い方です。そもそも名誉市民顕彰の目的は、単なる個人の栄誉にとどまらず、様々な分野での貢献を広く市民に知らせ、その功績を称えることで、市民に長く記憶されるようにすることが目的です。ところが、本市HPには名誉市民の功績が、ほんの一言ずつしか載っていません。

Q4 また、義務教育で郷土の歴史をどのように学ぶかで、その後の郷土愛は大きく変わることが考えられます。本市の場合、小学生むけの副読本の最後に、学習するかどうかは任意の「資料編」として、本市名誉市民22名の一覧があります。ところが、22名のうち解説記事があるのは2名だけで、他の名誉市民はやはり、一行ずつしか功績が書いてありません。この資料編は調べ学習のきっかけに使ってもらうと聞いておりますが、解説記事があるか・ないかで、その認知度も、教師や子どもたちが「この先人を調べてみよう」と思うモチベーションも、記憶に残るかどうかも、大きく変わるのではないでしょうか。名誉市民の解説は2人だけと選り好みをせず、少なくとも全員分、解説すべきと考えますが、教育長のご所見を伺います。
特に仙台市の場合、「支店経済」や「学都」という都市個性故、私自身もそうでしたが、転勤や入学等の理由で途中から仙台に入り、地域の歴史を知る機会のないまま、仙台に住んでいる市民の方々も多いと感じています。
Q5 すなわち、仙台は転入出が多い土地柄故に、地域に対する誇りを醸成するには、本市のような消極的姿勢では不十分なのは無論のこと、なおさら、知らなかった人が知る機会をつくるために、かなり積極的な啓蒙活動が必要な土地なのではないでしょうか。例えば、地域の先人たちの功績を後世へ伝える拠点づくりや、生涯学習などの取り組みが考えられると思いますが、ご所見を伺います。
Q6 さらに過去の顕彰のみとどまらず、現在進行形で仙台・東北の発展に大きく貢献した人たちや取り組みを積極的に顕彰するなど、グローバル・スタートアップ・エコシステムを真にこの地で根付かせるために、お金をかけずともやれることはたくさんあると考えます。最後に市長のご所見をお伺いして、私の質問を終わります。
答弁 Answer
市長
A1 スタートアップ支援と郷土愛について(仙台で事業を続ける必然性の醸成について)
仙台である必然性を醸成することについてお答えを申し上げます。本市は、これまでイノベーションを生み出してきた東北大学をはじめとする知的資源があり、そしてまた東日本大震災を契機とした、地域のために貢献したいという機運の高まりや、内閣府の「グローバル拠点都市」としての認定など、スタートアップが生まれる土壌は確実に育ってきているところでございます。
しかしながら、成長の過程で域外へ流出するスタートアップも少なくないという課題もあり、ウェットラボ整備モデル事業など定着に向けた環境整備に取り組んでいるところでございます。加えまして、仙台の地で成長し続けるという意識を持っていただくために、コミュニティの形成の中で、歴史や仙台であることの意味などを伝えてまいりたいと考えております。先人たちが抱いた仙台への思いを、私どももしっかりと受け止めて、仙台だからこそ大学や地域の企業とともにスタートアップのこの地での定着に向けた環境整備など、新たなイノベーションを生み出し続ける都市を目指して、まい進してまいりたいと存じます。
A2 郷土愛の醸成に向けた顕彰の取組みについて
それから、郷土愛の醸成に向けた、顕彰の取組みについて、お答えを申し上げます。本市では、オリンピックメダリストなど、優れた業績により広く市民に感銘を与えた方などに「賛辞の楯」をお贈りしているほか、本市の振興発展に寄与された方を「市政功労者」として表彰してきたところでございます。また、産業経済やスポーツ、文化芸術、社会福祉など、分野ごとに表彰を行っているほか、スタートアップに関しましては、東北経済産業局と連携した「J-Startup TOHOKU」において、将来性のある有望な企業を選定する取り組みを行っております。今まさにご活躍をされている仙台ゆかりの方々を顕彰することを通して、そうしたご功績を広く周知をし、市民の皆様の郷土愛や地域への誇りの醸成につなげてまいりたいと存じます。
答弁 Answer
総務局長
A3 名誉市民に係るHPでの広報について
名誉市民に係るホームページでの広報についてのお尋ねにお答え申し上げます。本市に御縁が深く、学術、文化等の進展に貢献されました名誉市民の功績を広く市民の皆様に知っていただきますことは、本市への誇りや郷土愛を育むことにつながるものと認識をしております。これまでも、ホームページや市役所本庁舎ギャラリーホールなどを通じてご紹介をしてきたところでございますが、現代社会の礎となった名誉市民の様々なご功績を、さらに多くの方により深く知っていただくことができますよう、まずはホームページの充実を図ることをし、掲載内容等について検討してまいりたいと存じます。
答弁 Answer
経済局長
A4 産学官連携の歴史の発信について
産学連携の歴史の発信についてでございます。本市における産学連携の足跡は、先人たちが仙台から世界へ挑戦を続けてきた歴史でありまして、その実績のみならず、地元へかけた思いも含め、私たちは改めて学ぶ必要があるものと認識しております。今年度新たに、本市のリサーチコンプレックス形成に関するウェブサイトを開設することとしておりまして、この中で本市の産学連携の歴史も含めて発信することで、スタートアップの定着や域外からの投資を促し、イノベーションの創出につなげてまいりたいと存じます。
答弁 Answer
教育長
A5 副読本における名誉市民の解説記事について
まず、副読本での名誉市民の解説についてでございます。小学校中高学年で使用している副読本「わたしたちのまち仙台」は、本市の社会的・歴史的事象の基本的な部分を学ぶものです。この副読本は、各教科等の授業内容と関連付けた学習で活用しているもので、小学3年生が理解できるよう、丁寧かつ平易な表現で多岐にわたる内容を記載しており、名誉市民お一人お一人を詳細に紹介することは難しいところではございますが、今後、市ホームページを閲覧できるよう副読本にQRコードを掲載するなど、一人一台端末の環境も生かしながら、児童が興味を持ち、主体的に調べることができるよう工夫してまいります。
A6 積極的な啓蒙活動について
次に、地域の先人たちに係る生涯学習分野の取組についてでございます。市民の皆様が地域の歴史や本市ゆかりの先人の功績を学ぶ機会を設けることは、地域への誇りや愛着の醸成につながるものと認識しております。これまでも、科学館や天文台における、各分野で功績のあった先人に関する展示や、図書館における、地域ゆかりの人物に関する資料を紹介するコーナーの設置など、各施設の特性に応じた取組を行ってまいりました。また、博物館や市民センターなどで実施する地域の歴史を題材とした講座や、いわゆる地元学の活動でも先人について取り上げるなど、市民の皆様が学ぶ機会を提供してきたところでございます。引き続き、市民の皆様が先人の功績について、様々な形で学ぶことができるよう、工夫してまいりたいと存じます。
Q7 【再質問】副読本における名誉市民の解説記事について
小学生向けの副読本における名誉市民の解説記事について、再質問させていただきます。小学校3年生が分かるような表現は難しいという課題を克服した上でホームページに載せるのでしょうか、それとも大人向けの解説のままホームページに誘導するのでしょうか、伺います。
答弁 Answer
教育長
A7 【再質問】副読本における名誉市民の解説記事について
現在、副読本で取り上げておりますのは、本多光太郎博士と土井晩翠先生ということになりますが、この両者はいずれも、小学3年生が、例えば磁石を使った理科の授業を受けているとか、例えば荒城の月を聞いたことがあるとか、そうした、小学生にとっても身近な名誉市民ということで、お2人を取り上げているところでございます。その他の名誉市民について小学生にも分かりやすく説明をするということが将来的には必要だとは思いますが、まずは総務局がホームページを充実するということでございますので、QRコードを副読本に掲載することで、紙とデジタルの連携を強めていくと、そうした取り組みをまずは行っていきたいと考えております。
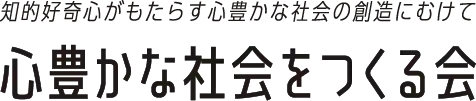


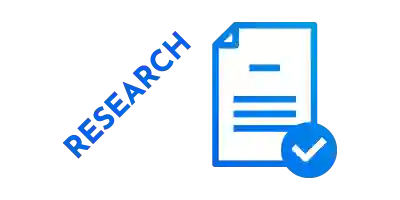
活動報告一覧に戻る