第10回「科学と社会」意見交換・交流会(ゲスト:MEMS研究者の江刺正喜さん)の参加者を募集します(2025.1.24開催)

心豊かな社会をつくる会(代表:大草芳江)では、知的好奇心がもたらす心豊かな社会の創造にむけて、「科学・技術の地産地消」具現化のアプローチを多角的に模索するために、「科学と社会」をテーマに、各界から毎回多彩なゲストを迎え、宮城の日本酒を交えながら、ざっくばらんに政策立案に資する議論を行うニュータイプの意見交換会を定期開催します。
「科学と社会」についての捉え方は、立場によって異なります。議題は、ゲストが「科学と社会」をどのように捉えているかからスタートし、その切り口から、参加者同士で議論を行います。議論の様子は、市民参加型の政策立案プロセス検証の一環として公開することにより、広く社会と共有します。
第10回のゲストは、IoT社会の実現に欠かせないキーデバイスである「MEMS(Micro Electro Mechanical Systems/微小電気機械システム※)」の世界的権威である江刺正喜さん(株式会社メムス・コアCTO、東北大学マイクロシステム融合研究開発センター シニアリサーチフェロー)です。
※ MEMS(Micro Electro Mechanical Systems/微小電気機械システム)とは、シリコンウェハー等の上に電子回路やセンサ、機械的に動くアクチュエーターなどを半導体微細加工技術などを利用して作り込んだ部品。近年、MEMSは車やスマートフォン等への搭載を通じて社会生活への浸透が進んでいる。
江刺さんは、「MEMS」という言葉すらなかった1970年代から、半導体微細加工技術をベースに多様な知識でセンサなどを作る研究を開始し、多くの研究者・技術者を育てるとともに、数々のMEMSの実用化に貢献されてきました。その功績により、紫綬褒章(2006)やIEEE Andrew Jun-ichi Nishizawa medal (2016)、瑞宝中綬章(2022年)等、数々の賞を受賞されています。
特に、研究開発が社会的価値を創造するまでのプロセスには、一般的に「死の谷」と呼ばれるボトルネックが存在し、このような「死の谷」を乗り越えることが「イノベーション」ですが、江刺さんは、たとえ競合企業であっても相互に学び合い、情報を共有化するオープンなコラボレーション(共創)の場を創出し、イノベーションを引き起こした成功事例として、日本の政府や企業はもとより、世界中の企業や研究機関から絶大な支持を受けています。
イノベーションを引き起こすオープンなコラボレーションの場を、江刺さんはどのように実現してきたのでしょうか。江刺さんから「オタクあがりのモノづくり人生」と題して、そのプロセスをお話いただき、参加者同士でざっくばらんに議論いたします。
開催概要 Summary
【名称】第10回「科学と社会」意見交換・交流会
【日時】2025年01月24日(金)19:00〜21:00
【場所】綴カフェ(仙台市青葉区北目町4-7 HSGビル1階 https://tsuzuri.jp/)
【ゲスト】江刺正喜さん(株式会社メムス・コアCTO、東北大学 マイクロシステム融合研究開発センターシニアリサーチフェロー)
 [略歴] (えさし・まさよし)1949年仙台市生まれ。1971年東北大学工学部電子工学科卒。1976年同大学院博士課程修了。同年より東北大学工学部助手、1981年助教授、1990年より教授となり、2013年定年退職。現在 、株式会社メムス・コア CTO兼 東北大学 マイクロシステム融合研究開発センターリサーチフェロー。半導体センサ、マイクロシステム、MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)の研究に従事。主な受賞歴は、日本IBM科学賞(1993)、SSDM Award(2001)、第3回産学官連携推進会議 文部科学大臣賞(2004)、第54回河北文化賞(2005)、紫綬褒章(2006)、IEEE Andrew S.Grove Award (2015)、IEEE Andrew Jun-ichi Nishizawa medal (2016)、瑞宝中綬章(2022)等多数。
[略歴] (えさし・まさよし)1949年仙台市生まれ。1971年東北大学工学部電子工学科卒。1976年同大学院博士課程修了。同年より東北大学工学部助手、1981年助教授、1990年より教授となり、2013年定年退職。現在 、株式会社メムス・コア CTO兼 東北大学 マイクロシステム融合研究開発センターリサーチフェロー。半導体センサ、マイクロシステム、MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)の研究に従事。主な受賞歴は、日本IBM科学賞(1993)、SSDM Award(2001)、第3回産学官連携推進会議 文部科学大臣賞(2004)、第54回河北文化賞(2005)、紫綬褒章(2006)、IEEE Andrew S.Grove Award (2015)、IEEE Andrew Jun-ichi Nishizawa medal (2016)、瑞宝中綬章(2022)等多数。
【費用】3,000円(綴カフェ軽食と宮城の日本酒の実費です。恐れ入りますが、価格上昇に伴い費用を改定させていただきました)
【定員】先着25名(定員になり次第、募集を締め切らせていただきます)
【締切】開催日の前々日まで
【申込方法】名前・所属・連絡先(当日つながる携帯電話番号)をご記入の上、メールにて以下アドレス info@yoshie-ohkusa.info までお申し込みください。
【主催】心豊かな社会をつくる会(代表 大草芳江)
【備考】議論の様子は、市民参加型の政策立案プロセス検証の一環として、無記名で議事録を作成し公開いたします。
【講演要旨】
「オタクあがりのモノづくり人生」 江刺正喜
私は半導体微細加工をベースに多様な知識でセンサなどを作るMEMS (Micro Electro Mechanical Systems) と呼ばれる技術に、学生時代から半世紀ほど関わってきました。半導体の世界で、微細化・高集積化のMore Mooreに対し、MEMSは多様化のMore than Mooreと呼ばれる流れで、システムの入出力部などで鍵を握る高付加価値の部品を供給する技術です。高密度集積回路(LSI)などと異なり多品種・少量であることが多いのですが、開発がボトルネックになります。その場合の開発には一連の半導体微細加工の他にもいろいろな設備が必要で、また広い分野の知識にアクセスできる必要があります。このため自由度が高い一連の設備を共用しながら、使い方や関連知識を伝えて利用してもらう「試作コインランドリ」が、仙台市青葉台にある東北大学の西澤潤一記念研究センターにあり、戸津健太郎教授がセンター長として運営しています。2010年に設置され、それ以来400程の機関 (334社) が人を派遣して利用し、独立採算に近い形で運用されております。利用者からの要望を行政に伝え、2013年から製品製作もできるようになっています。またサンプルなどを見られる5部屋の展示室や、知識提供に役立つようにExcelのキーワード検索で探せる1,000冊の文献ファイルなどがあります。このような仕組みに至った経緯をお伝えすることで、役に立つ仕組みづくりにつながるような話をさせて頂きたいと思います。
私は東北大学の西澤研究室の設備を参考にして半導体微細加工装置を自作し、また医療用の化学センサや集積回路製作など広く関わってきました。2013年に工学研究科を定年退職しましたが、教授時代は多いときで250回/年ほど会社の人の相談に乗って、130社程の会社が平均2年程受託研究員を派遣していました。日本経済新聞社が2003年に会社から集めたアンケートで、最も頼りにされる研究室と評価されました(日経産業新聞 2003年12月12日)。
開催報告 List
- 第9回「科学と社会」意見交換・交流会をスパコン科学者の川添良幸さん(東北大学未来科学技術共同研究センター シニアリサーチ・フェロー、名誉教授ドットコム株式会社代表取締役)をゲストに迎えて開催しました(2024年12月26日)
- 第8回「科学と社会」意見交換・交流会を工学者の伊藤弘昌さん(元東北大学電気通信研究所長、元東北大学未来科学技術共同研究センター長)をゲストに迎えて開催しました(2024年11月29日)
- 第7回「科学と社会」意見交換・交流会を光化学者の福村裕史さん(元東北大学理学研究科長、元仙台高等専門学校校長)をゲストに迎えて開催しました(2024年10月25日)
- 第6回「科学と社会」意見交換・交流会を地球生命科学者・深海生物学者の北里洋さんをゲストに迎えて開催しました(2024年07月30日)
- 第5回「科学と社会」意見交換・交流会を宇宙物理学者の二間瀬敏史さんをゲストに迎えて開催しました(2024年5月24日)
- 第2回「科学と社会」意見交換・交流会を経営学者の大滝精一さん(至善館副学長・東北大学名誉教授)をゲストに迎えて開催しました(2024年2月26日)
- 第1回「科学と社会」意見交換・交流会を文部科学省の斉藤卓也さん(理化学研究所経営企画部長、前文部科学省人材政策課長)をゲストに迎えて開催しました(2023年11月29日)
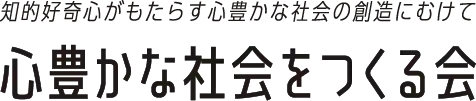

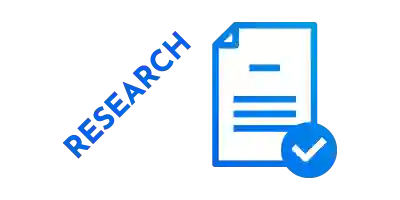
イベント実施報告一覧に戻る